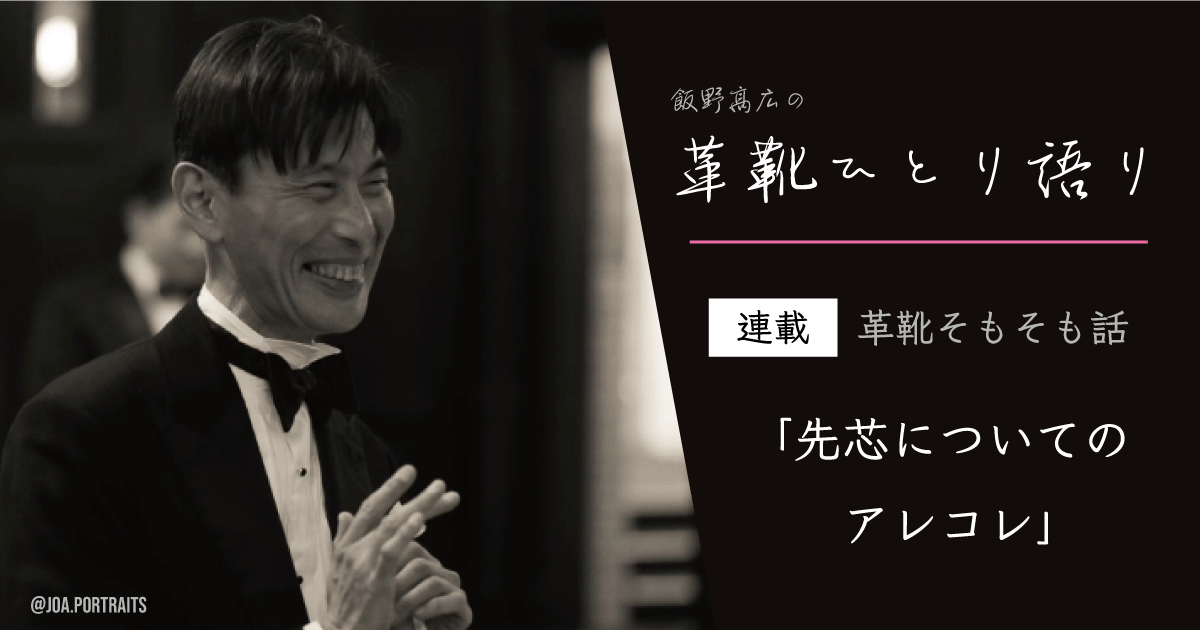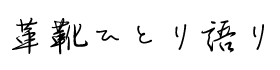革靴に関する深すぎる情報を発信する「革靴ひとり語り」
今回も深い革靴沼、もとい奈落にお連れします。
先芯の話から始めよう
靴磨きのビフォーアフターで印象が激変するつま先。
ここが綺麗に仕上がるとホッと一息だし、履いていてここに少しでも擦れが生じれば、猛烈に萎えまくる…そしてここの要となるパーツが、アッパーとライニングの間に挿入する芯材 = 先芯(さきしん)だ。今回はその先芯についてのあれこれ。

(このつま先部分に入っているのが先芯だ)
先芯ってなんで必要なの?
先芯がなぜ必要なのか?それは先芯の3つの機能に由来する。
1. つま先や足の指を守る
これを入れることで、雨や小石などの外部の障害から足のつま先をより確実に守る、一種のカバーの役割を果たす。
2. 靴の形状を保持し壊れにくくする
先芯はトウシェイプを維持するだけでなく、靴全体の形状を守る補強材にもなっているのだ。
3. 足、特につま先を靴に適切に固定し、歩きやすくする
不要な横ブレを防ぎ、足の動きのエネルギーを最適化する重要な使命も帯びていることをどうか覚えておいてほしい。
先芯って何から作られてるの?
先芯の重要性をざっくり理解してもらったところでここからが奥深い話。
まず、革靴の先芯でかつて最も用いられていたのは、素直に牛革。インソールやアウトソールと同様のタンニン鞣しのヌメ革で、靴の用途や大きさに応じて最も丈夫な層=銀面が付いたまま用いる場合もあれば、それを削った床革として用いる場合もある。
他の主要パーツと同じ素材だからか、あざとさのない自然なトウシェイプに仕上がる。ただし装着に手間が掛かるため、今日ではこれを用いるのは事実上、ビスポークの革靴など手作業でのみの成形=釣り込みを行う革靴のみとなっている。
そのため、今日の主流は革の端材を砕いた上で再成形した「レザーファイバーボード」や、ジーンズのラベルでお馴染みのパルプボードや和紙系の「疑革紙」、それに不織布などだ。これらに接着剤・有機溶剤・熱可塑性樹脂などを含侵させることで短時間での成形を可能にしている。機械での釣り込みの進化・高度化に合わせて素材の改良が進んだこともあり、今日では高級な革靴でも既製品なら大抵はこれと考えてよい。
一方、革靴の種類で先芯の素材が変わることもある。安全靴やワークブーツ系の革靴では、先芯には薄板鋼板や合成樹脂が用いられる。日本ではJIS規格で耐衝撃性や耐圧迫性が厳密に管理される、極めて重要なパーツだ。他の素材に比べ通気性にはどうしても難があるものの、つま先自体を守るほうが遥かに優先する。筆者は前職で鉄鋼メーカー勤務だったが、安全靴着用が義務図けられている製鉄所の現場の方の多くが水虫に悩まされていたのを今でもはっきり覚えている。
逆に、つま先の柔軟性・軽快性を最優先とした靴、例えばライニング無しのローファーなどでは確信犯的にこれを挿入しない、若しくは最小限にしか入れない場合もあるのだ。実に奥深い。
先芯は案外、歴史が新しいのだ!
実は先芯が革靴に本格的に導入されるようになったのは19世紀期後半からと、そこまで古くはない。左右で別形状の革靴が再登場したのとほぼ同じタイミングなのが興味深い。実はこれ、近代的なコンパスの登場など産業革命の副産物である「製図の進化」が日用品の進化をもたらした典型事例で、言わば「最先端の」左右別トウシェイプを維持する目的で装着された訳だ。
やがて先芯はつま先の補強・保護も兼ねるようになり、1880年代には「デザイン」としての要素も帯びるようになってゆく。機能(FUNCTION)がやがてファッション(FASHION)になってしまう歴史の宿命を、先芯も歩んだのだ。存在感を全くアッパーの表面に見せないもの、表にこそ見せないが封入する際の目安線だけは表示したもの、敢えて外に露出させた分厚いもの… その違いこそが今日のキャップトウとプレーントウの違いそのものであり、先芯の登場はいわば、今日的な紳士靴のバリエーションの原点でもある。
因みに日本に欧米的な革靴製造のノウハウが伝わったのも、まさにこの先芯が革靴に付き始めたタイミング。例えば日本最古の革靴メーカーである大塚製靴は、先芯の初期段階のもの(当時の製造工程にちなんで「鼻まくり芯」と呼んでいた)を、なんと1870年代には独自に考案している。
先芯はその機能性から必要とされ歴史は浅いものの技術とともに進化を遂げてきた。そして、機能美としての役割からデザインの要素が取り入れられ、目的に応じて素材が選ばれるほどになった。
重要なのは、単に先芯の歴史や素材について広辞苑的な解釈を深めることではなく「この革靴にはどんな先芯がなぜ使われているのだろうか?」「制作の意図を汲むとするとどのようにメンテナンス、磨きをすることが求められるのだろうか?」といったことに想いを馳せることなのではなかろうかと愚考する。ぜひこの奥深い世界に足を踏み入れ、自分だけの解釈、グラデーションを追求していただければ幸いである。