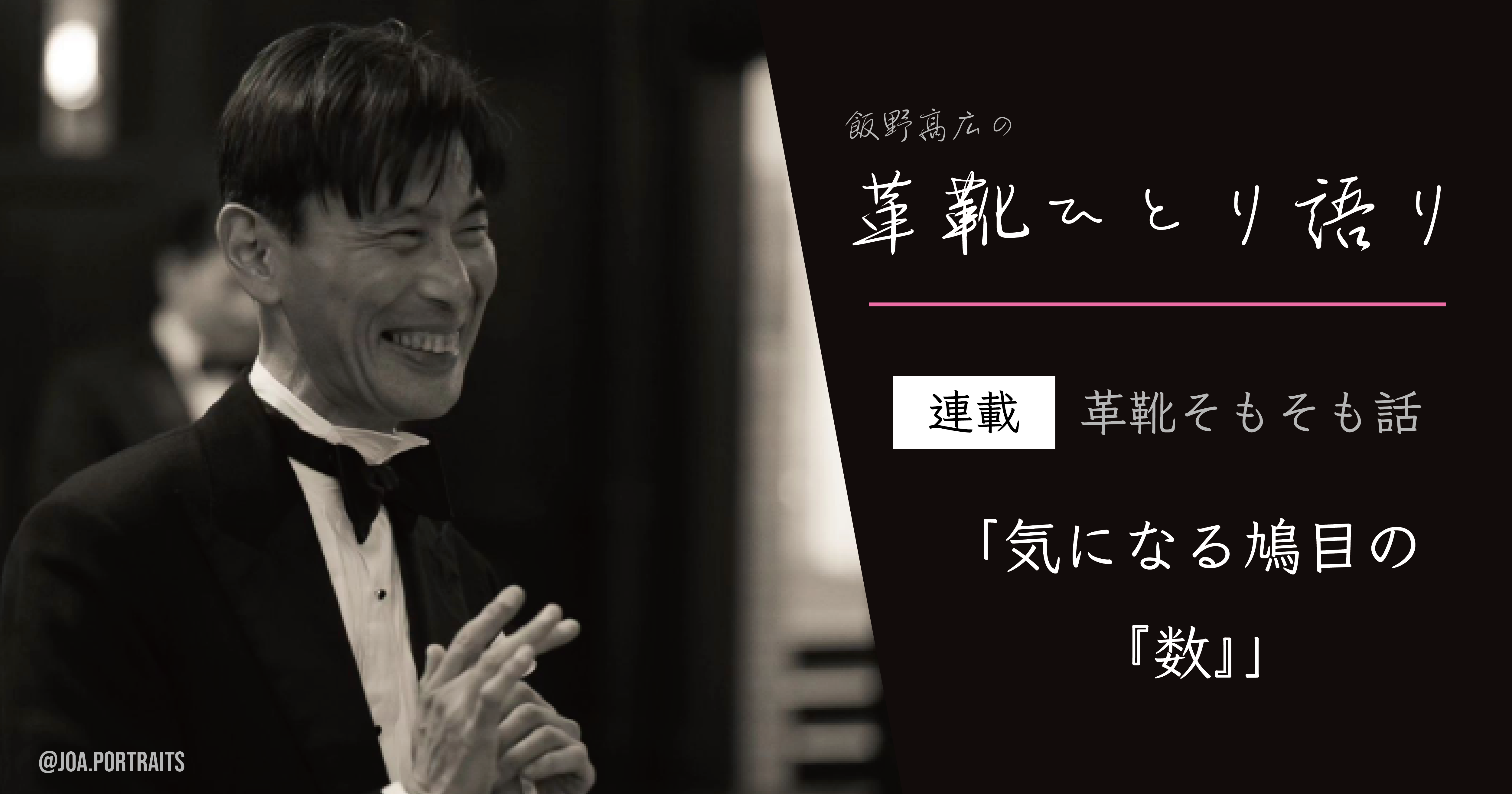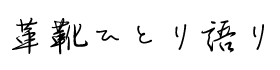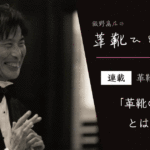革靴に関する深すぎる情報を発信する「革靴ひとり語り」
今回は、いったん気になるともう、こだわらざるを得ない! 革靴の鳩目の「数」の話
鳩目が “どうしようもなく” 気になる
靴をお手入れする時、「今回は靴紐、全て抜いてしまおうか?鳩目に通したままでいいかな?」は靴好きなら必ず悩んだ経験があるだろう。特に鳩目の数が多いものはなおさら。今回はそんな鳩目の「数」について、色々と例を挙げて語ってみたい。相変わらずのマニアックな沼語りになってしまうため、その点予めお詫びしておく。
数が少ないと優雅な印象
例外も多いが革靴、特にドレスシューズ系で申せば鳩目は概して、少ないものの方が優雅な印象となる。反対にある程度以上多くなると、より活動的に映りがちで実際にもフィット感の微調整を行いやすい。貴族階級の足元がメンズでも鳩目なしのスリッポン系が圧倒的主流だったフランス革命前までの価値観を、未だに引きずっているのだ。まあ、彼らは立場上、ピッタリサイズの革靴を当たり前に誂えることができたので、靴紐と鳩目で「微調整」をする概念そのものが芽生えなかった訳だが… スリッポン構造のオペラパンプスが今日の革靴でも最高礼装の立ち位置に残っているのは、まさにその名残と言えよう。
そんな観点で見渡すと、鳩目の少ないものの代表例は2穴のコルテのアルカや3穴のベルルッティのアレッサンドロではないだろうか? いずれも「美しさ」を重んじるフランスのブランドの傑作であるのは、偶然なのか必然なのか… 特にアルカは、構造が軍靴由来の外羽根式にもかかわらずある種の貴族性を帯びた麗しさが思いっきり前面に出るからか正直、万人に似合う靴とは言い難い。ただその分、一目惚れする人の心理もわかる。

出典:ベルルッティ アレッサンドロ デムジュール レザー オックスフォード

Corthay Arca(筆者撮影)
3穴と言えば、少し前までイギリスの靴メーカーならどこでも必ずラインナップされていた外羽根式のVフロントプレーントウの存在も忘れてほしくない。20年以上前、ヨーロッパでクラシックのコンサートを聴きに行った際、ロンドンでもウィーンでもディナージャケット姿の足元に、アッパーに黒のボックスカーフを用いたこれを合わせている人が案外多くて驚いた経験がある。
パテントレザー(エナメル)のオペラパンプスでも、内羽根式の5穴のプレーントウでもなく、綺麗に磨かれた3穴のこれである。仰々しさがなく「礼装が日常生活の延長線上に”まだある”」ことを教えてくれたようで妙に安心したことを鮮明に覚えている。
あまり見掛けなくなってしまったが、汎用性の高さは絶対に再評価されるべき一品であろう。

(筆者はこの作り手の計らいと使い手の所作にイギリス精神・ダンディズムを感じてしまうのだ)
意外と少ない4穴。最も一般的な5穴。
4穴は立ち位置が奇妙な「鳩目業界の不思議ちゃん」である。
リンゴの皮剥きを思わせる螺旋状のパターン構成が今でも目を惹く2009年イヤーモデルを筆頭に、パリのロブには意欲作が幾つか存在するものの、個人的には4穴はカントリー系、とりわけトリッカーズのバートンやウッドストックの印象が非常に強い。本来の用途が用途なだけに、鳩目の数を多くしてフィット感を高めたほうが有用な気もするが… いや逆に、これらは厚手の靴下を履く前提で設計されているから、つま先側を靴紐でホールドし過ぎない方が好都合なのかな? それとも数を敢えて削るのを通じ、靴紐が野山の木の枝などに引っ掛かるリスクを減らす目的?
謎は深まるばかりである。ともかくも、機能美を追求する方向とファッションに昇華させようとする方向の狭間を行ったり来たりする不思議な存在。AB型のようなミステリアスな魅力がある(筆者目線)。

出典:Web Magazine OPENERS
(鳩目一つとってもロブのクリエイティブは奥深い洞察に裏付けされているのである)
一方、くるぶしを隠さないシューズ丈の革靴で、メーカーやブランドに関係なく最も一般的な鳩目の数は、やはり5穴だ。
甲を覆ってフィット感を高めるのに多からず少なからず、最も適切な数であるとともに、視覚的にもバランスに優れているからかもしれない。また、靴紐の通し方で最も一般的な「パラレル」は、コツさえ覚えればこの5穴は、4穴や6穴のものより左右の長さを遥かに簡単に合わせることが可能。斯様に様々な合理的な理由から、この数に自然に集約されたと思われる。
6穴以上は活動的で精悍なイメージ
6穴仕様はアレン・エドモンズのものを筆頭に、アメリカ靴の内羽根式のイメージ。
オールデンはアメリカ靴では例外的に内羽根式でも5穴が圧倒的に主流だが、外羽根式になるとモディファイドラストやミリタリーラストのモデルもこの数。最近アーチケリーが復刻させたネイビーラストの外羽根式も6穴だ。鳩目の対を多くすることで、フィット感をいっそう高めようとする明確な意図を感じる。その一方で、いわゆる「ホールカット」構造の革靴も6穴仕様が多い。こちらは靴の表情を平板にさせないためのデザイン上の工夫なのだろう。

出典:Trading Post
(アメリカ靴らしい機能性を重視した靴はフィット感が高まる6穴なのである)
かつてはアメリカのメーカーの内羽根式には7穴のものも多かった。アレン・エドモンズのそれはブールバード(Boulevard:フランス語で「大通り」を冠したレザーシューズ)って名前だったっけ? 確かに多い鳩目のお陰で、その名の通り賑やかな「大通り」って感じだったよなぁ…
なおアメリカ靴の内羽根式は、特に6穴や7穴のものは鳩目の横間隔が狭い傾向にある。これは単に見た目の精悍さを高めるためだけでなく、靴紐で足を「左右方向に幅広く」ではなく「前後方向に細長く」押さえるのを通じ、より多くのタイプの足(=より多くの人種の足)に合せようとするアプローチにも思える。
以上、鳩目の「数」についてつらつらと語ってみた。
かなりマニアックではあるが、靴全体のシルエットや印象を決定づける「革靴設計の根幹」であることがお判りいただけたかと思う。
お手持ちの革靴の鳩目はいくつだろうか?そしてそれはなぜだろう?
ごく一部の敬虔な読者の皆様は気になって仕方なくなってしまったのではなかろうか。
あ、そういえば大分前だけど、パリのジョンロブの内羽根式フォーマルプレーントウ=ガルニエが、「Ⅰ」から「Ⅱ」にモデルチェンジした際に5穴から6穴に増えてひどく驚いたことを思い出した。あれは恐らく、木型を8695番からよりロングノーズな7000番に変えたので、そうしないとデザイン的に「だらける」と考えたから。でも…ひょっとしたら…その後の礼装全体のカジュアル化を予測した上での変更でもあったのかも?
・・・などと気が散るほど思いを巡らせ始めたそこのあなた。
「ようこそ、めくるめく鳩目の世界に」