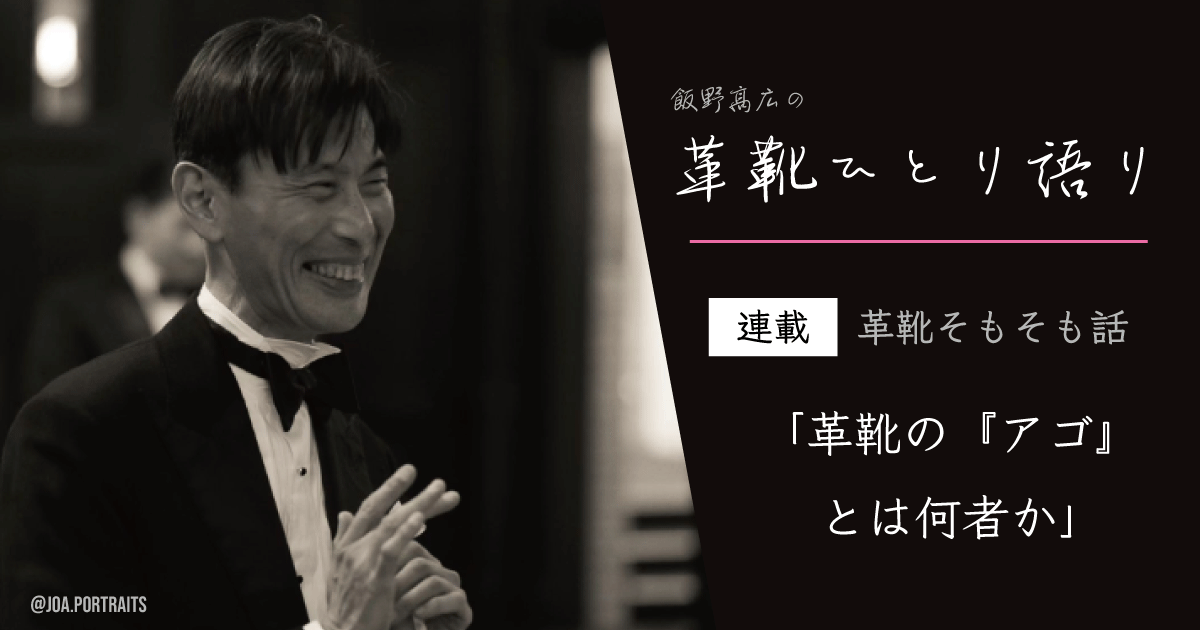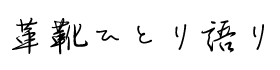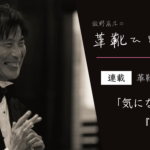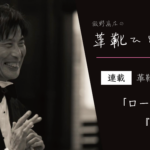突然だが、皆さんは革靴の『アゴ』をご存知だろうか?革靴のヒールを形作るニクい曲線のことである。
先日とある取材で、靴を何足か撮影スタジオに運ぶ機会があり靴を一足一足並べる内に「あれ?この靴ってこんなアゴだったっけ?」とじっと見入ってしまった。ゆうに十分ほどは立ち止まってしまったのでは無いだろうか。
気になり始めたら止まらない性分ゆえ、撮影が押してしまうほど「ハマって」しまったのである。
そんなわけで今回は、革靴のヒールのつま先側=アゴ(刳り)の形状について、いつも以上にドロドロと語ってみたい。
『アゴ』って何だ?実物から思考を巡らせてみる
まず、ヒールのアゴは以下の3種類に大別される(気がする)ため、それを筆者なりの分類について紹介することにする。
何はなくとも、分けて考えてみることで収拾をつけていこうという試みである。なお、筆者の主観が多分に入っていることを予めお断りする。というのも、『アゴ』に関する研究はほとんどないと認識しており正解が定まっていないためである。
そのため、ボトムアップで実物ベースに整理するアプローチを採り考察を重ねてみることにする。これこそ、ひとり語りの醍醐味たる所以である。なお、これ以降に登場する写真のヒールは全て「右足」のものであることを、予めお断り申し上げておく。
#1. 対称的な弧状
綺麗に刳りが設けられたもので、これが革靴では一般的。よく見る形状である。
歩行時に足の「けり出し」をより円滑に行うための何気なくも効果覿面の一工夫がある。
この「弧」の勾配が”キツい”、”ユルい”の違いが、メーカー・ブランド、モデルによって種々様々に存在するのが面白いところでもある。

ビスポークの靴のアゴはやはり綺麗な弧を描く
#2. 直線
歩行の快適性以上に姿勢の安定性を重視する場合はこれに限る。安定性を追求した結果、ハイヒールは大抵この形状を採用しているのである。実に機能美に溢れているとは思うまいか。
また、この直線上の「アゴ」は「ライディングヒール」という異名を併せ持つ。これは、本格的な乗馬用ブーツは必ずこの仕様になっていることに由来している。同じく直線になっている鐙(あぶみ)の端にヒールがロックされ、足が前に放り出されるのを防いでいるのだ。
この場合、騎乗時につま先を馬の身体に干渉させず足と脚を広げやすくするため、外くるぶし側の辺を若干長めに設定するのも特徴と言える。
先人の工夫、叡智が現代に受け継がれている様は実にロマンチズムに溢れている。

こちらは典型的なライディングヒールなので、外くるぶし側(写真の下側)の辺が長くなっている。
#3. 非対称
19世紀末、イギリスの外科医によって考案された形状である。外科医の名にちなんで「トーマスヒール」と呼ばれることもある。
これはアゴに「うねり」を入れた上で内くるぶし側の辺を極端に長く設計したもので、偏平足・外反偏平足の矯正に向くとされている。
単に艶かしい曲線を追求しているわけではない。考え抜かれた設計者の創意工夫を体現しているのである。
尚、滅多にお目に掛れないが、内反足の矯正を目的とし逆に外くるぶし側を極端に長くした「逆トーマスヒール」も存在が確認されている。「逆トーマスヒール」を巷で見かけたら即確保すべきなのは言うまでも無い。ただし本来の用途とは異なるため、一般の人向けには履き心地は保証しないことをお断りしておく。

内くるぶし側(写真の上側)の辺が極端に長いのがトーマスヒールの特徴。
筆者はこの3つの型を『アゴ』の基本のキと位置づけており、この定義を踏まえて革靴メーカー・ブランドの特徴について思いを巡らせてみることにする。ここでは、筆者が特に関心を寄せている「クセ」のある革靴メーカー・ブランド3社について考えを整理してみよう。
ジェフリーウエスト
トップバッターたる1社目は日本には殆ど入ってこない英国ブランド「ジェフリーウエスト」だ。
読者に馴染みが薄いであろう同社を一番打者に据えたのは、度肝を抜かされるその形状に理由がある。
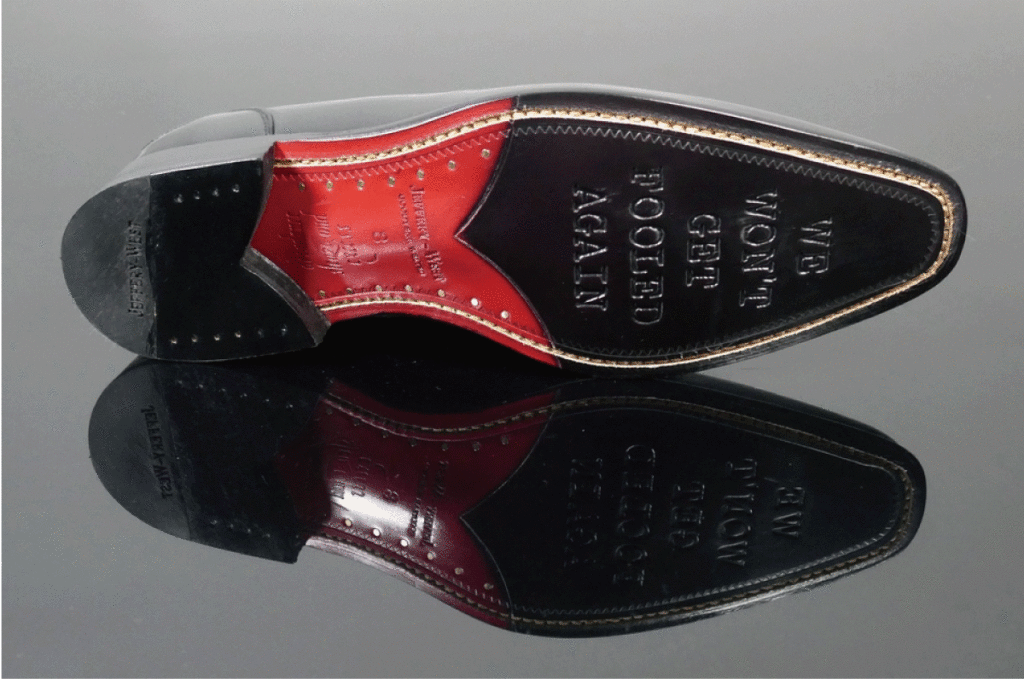
ご覧の通りほぼチューリップ!これが生粋の英国製なのだから面白い。
何と#3:非対称 の変型と言うには無理があるほどの、まるでチューリップの花のように「中央部が割けたような二弧」を描いているのだ。
その名もズバリ「クレフトヒール(Cleft Heel:割けたヒールの意)」。
どうやら古の乗馬ブーツのディテールを参考にしたようだが果たして真相やいかに、といったところ。
同ブランドは、嘗てからのモットーを“Infamous English Shoes”=某英国メーカーのもののパロディ、としているだけあって、グッドイヤー製法のものは創業時から一貫してチーニーが請け負っている。時同じくして90年代にこのブランドのチーニー側の担当だった人物が、やがてステップアップを果たし、自身の名の付いたメーカーとアトリエを立ち上げ英国紳士靴産業界のスターに大化けするわけだが、読者の皆様は誰だかお分かりだろうか?ひょっとしたらこの割けたアゴも、彼のアイデアだったのかもしれない。そう考えると実に興味深い。
J.M. WESTON
2社目は意外に思われるかも知れないがウエストンを紹介したい。

ウエストンの代表選手、ローファー#180のアゴはスパッと直線。なお、ゴム部の形状が現行品とは異なります。
ダービーやでトリプルソールフルブローグなどの外羽根式の紐靴や例の大定番ローファー・#180には、レザーソール仕様の場合は#2:直線 が採用されている。がしかし、同じ外羽根式でも性別を問わずファンの多いUチップ・ゴルフは、標準のラバーソール仕様も希少なレザーソール仕様も#1:対称的な弧状 なのである。なぜかくも異なるのか?
同社のラバーソール・ヒールは専業メーカーからの供給なので先方の基準に合わせている一方、レザーソール・ヒールの材料は子会社のバスタン社製。つまり製造上の都合なのかも知れない。そう考えると、設計者が意図しない組み合わせが偶然にも誕生していることになり、数奇な運命を感じざるを得ない。正統派でありながら絶妙な変化球を放ってくれる存在、それがJ.M. WESTONなのだ。
Alden
最後は大いなる謎と混沌をもたらす存在。それはやはりオールデンだ。
最早説明不要、コアなファンが多い同社製品をうまくカテゴライズすることには極めて困難を伴う。まず、インディーブーツには#3:非対称 に近いアゴを採用している。そして、同社ならではのモディファイドラストを用いたものには、#1:対称的な弧状と#3:非対称 の中間のような特殊な形状を持つ。これらは機能性を重んじる同社のスタンスだと好意的に解釈してみることとする。ここまでは納得感が無いわけでは無い。

トーマスヒールの要素を多く含む、オールデンのモディファイドラストのアゴ
迷宮に迷い込んでしまうのはここからである。
外羽根式のプレーントウの名品・#990のみならず、アッパーをエナメルとした内羽根式のフォーマルプレーントウを含めたドレス性の高い紐靴、そしてローファーの代名詞たる#986ですら、アゴはただただひたすらに#2:直線 なのだ。思い出していただきたい。直線 は「ファッション性」ではなく「機能性・安定性」を追求した結果生まれたものなのである。
BOOT MAKERとしてのプライドなのか、それとも何らかの、筆者の認識の枠外にある機能を考慮したものなのか。この起用には謎が深まるばかりである。
そしてまた期待を裏切るように、ミリタリーラストの外羽根式や、コープリーラストのローファーに関しては、弧の曲率こそ違いがあるものの#1:対称的な弧状 を描く。歩行量が多くなる可能性が高いミリタリーラストのものはともかく、ローファーの不徹底ぶりにはツッコミを入れざるを得ない。
食傷気味の読者を置き去りにしつつ。更に筆者が驚いたのは、タッセルスリッポンとこれと同じアバディーンラストを用いるドレスローファーのアゴに至っては、何故か#1:対称的な弧状 を採用している点である。
おいおい、そこは#2:直線 という話ではなかったか。なぜそこで裏の裏をかいて正統派路線なのか。もはや小気味良さすらある
(そしてショップ別注商品はさらに例外もあるのだから型にはまらないにも程がある)
「考えすぎなのかもしれない」と思う瞬間が無いことも無い
革靴の宇宙代表とも言える一流のメーカーであっても定石たる類型を逸脱する始末である。
ここまでの定義のブレを見ると「考えすぎなのかもしれない」と思わないことも無い。しかしながら「アゴ」を睨み続けると思わず考え込んでしまう性分。よってもう少しお付き合いいただくことにする。
例外はありながら、やはり靴は時代を映す鏡なのだ
過去に遡りさらにマニアックな話をしよう。アメリカントラッドの古の雄・ブルックスブラザーズがエドワード・グリーンに別注していた「ピール&Co.」ネームの靴は、アゴの違いで年代が判別できる、という何とも面白い特徴を持っていた。

こちらは70年代終盤のエドワード・グリーン製ピール& Co.ブルックス。最初の写真のアゴに比べカーブが明らかに緩い。
以前のものは#2:直線 だったが、70年代後半のものから緩めの#1:対称的な弧状 に変化し、末期の80年代終盤のものは通常のエドワード・グリーンと同様の綺麗な弧を描く完全な#1のシェイプに変化してしまった。
元々は英国のビスポークメゾンだったが、やがてチャーチが買収しアメリカ向けの別ブランドとして活用したアラン・マカフィーも、昔の製品に遡れば遡るほどやはり#2:直線。つまり時代を経るごとに緩やかにカーブを描いていくのである。
それを裏付けるように、19世紀末のアメリカのブーツカタログを紐解くと#2:直線 が圧倒的主流だった一方で、1930年代のイギリスの通販カタログを紐解くと、ブーツでも#1:対称的な弧状 が多い。
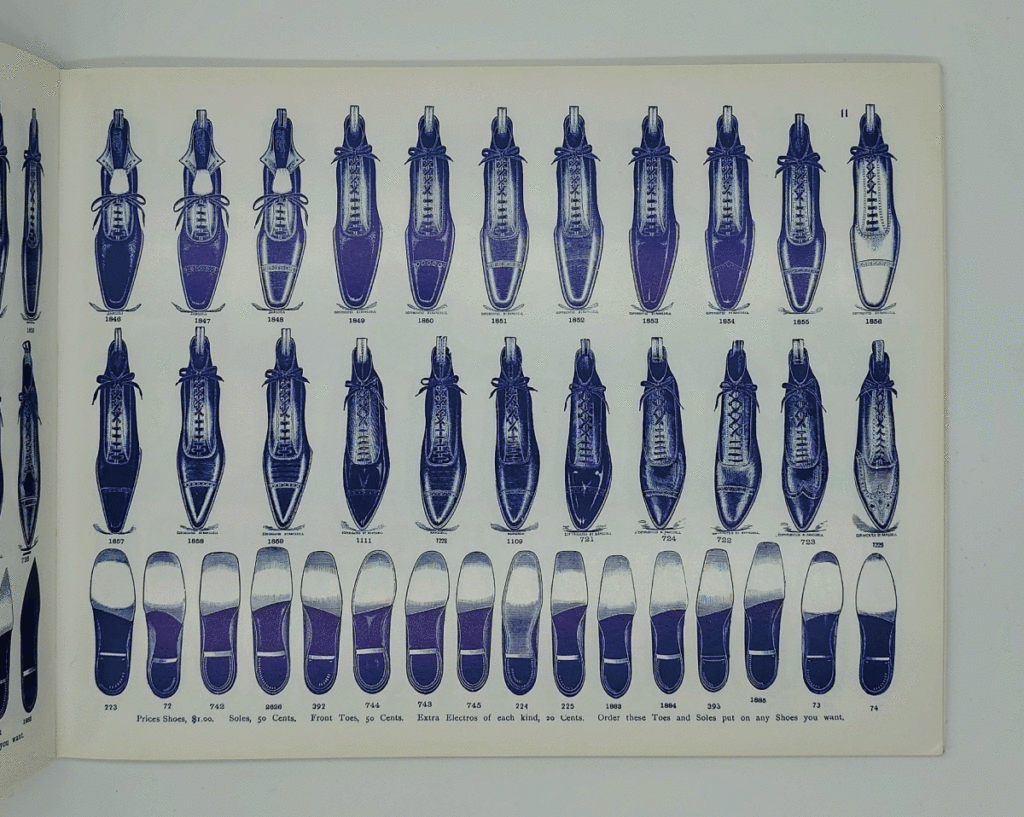
19世紀末のアメリカのブーツカタログ。直線的な形状を掲載している下段に注目だ

1930年代のイギリスの通販カタログ。チラと覗く「アゴ」の形状は弧を描いている
自動車の普及で、日常生活で「馬に乗る」機会が圧倒的に減少したのが、まさに両時代の中間に当たる。時代背景も合わせて考えると変遷の考察に深みが出ると言うものである。そこまで踏まえると、他の革靴メーカーでは次第にガチガチの乗馬ブーツにのみ#2:直線を採用するようになった可能性が示唆される。一方、実はJ.M.ウエストンやオールデンのスタンダードモデルでは、特段何も考えずに惰性で残していただけなのかもしれない。これが自然である。
付け加えるならば、ゴルフやタッセルスリッポンは、いずれも戦後に彼ら自身が設計したモデルである。だからこそ、過去の因習に変に囚われることなく#1:対称的な弧状 を採り入れることが出来たと考えれば、スッキリと整理ができるはずであるが果たして。
ここまでついてこれている読者がいかほどいるかは甚だ疑問である。ただし、ここまで脱落せずに追従できた敬虔な読者がいるとすれば、もはや本記事の読破をそこそこにシュークローゼットの靴裏を確認し製造年を調べ始めていることだろう。
先人が実は深く考えもせずに作り上げた革靴の1パーツの形状について、渾々とあてもなく考え続ける。そんな週末も一興ではなかろうか。